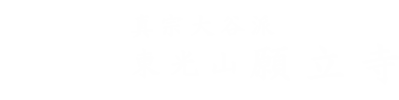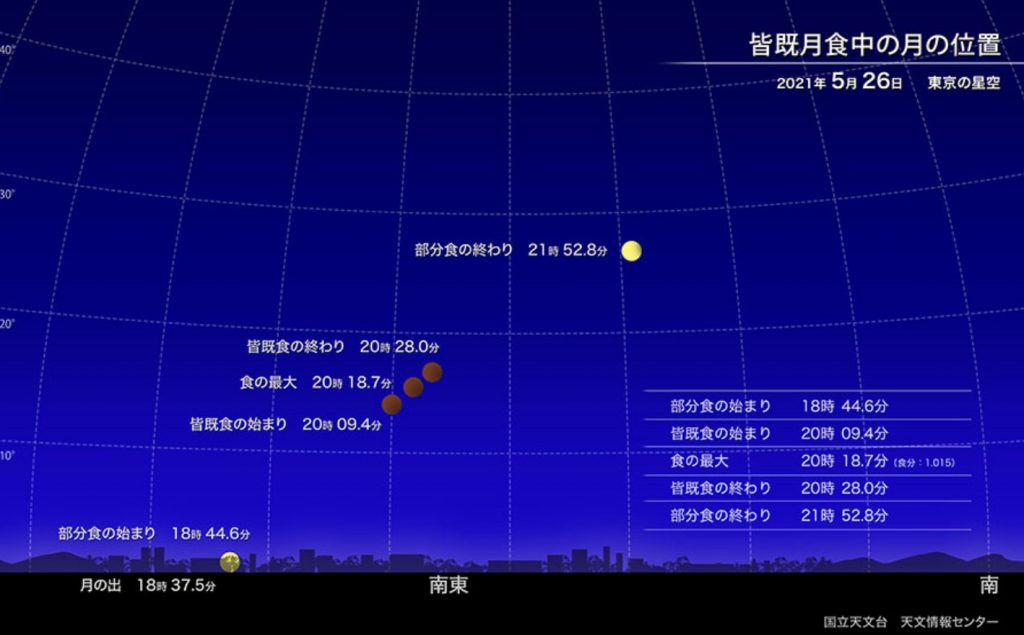府下緊急事態宣言に伴う、法務の自粛・中止について
2021.7.31|願立寺日記
大阪の新型コロナ感染者数が1040人/日となり急激な増加となっています。
また、デルタ株と呼ばれる変異ウイルスの脅威があるようです。
政府からも8/2〜8/31までの再度の緊急事態宣言が発令されることが決定
しました。残念ですが念のため、お寺の法務も下記のように自粛、中止を
させていただきます。
東京オリンピックではメダル獲得も多数で、勝っても負けても選手のみな
さんの頑張りが励みになります。家で静かに応援したいものです。
*********************************************************************
○緊急事態宣言中
月参り・・・自粛し毎朝8時に寺勤めとします。宜しければお参りください。
自宅勤め希望の方は連絡ください。お参りします。
法事・・・・ご予約いただいた年忌等、感染対策をしてお参りします。
葬儀・・・・感染対策をして実施します。
婦人会・・・8月は中止します。
お逮夜法座・8月は中止します。
★盂蘭盆会・8月15日正午 感染対策して実施します。
※緊急事態宣言が解除されましたら、平常法務に戻ります。
*********************************************************************