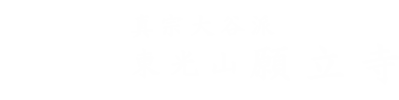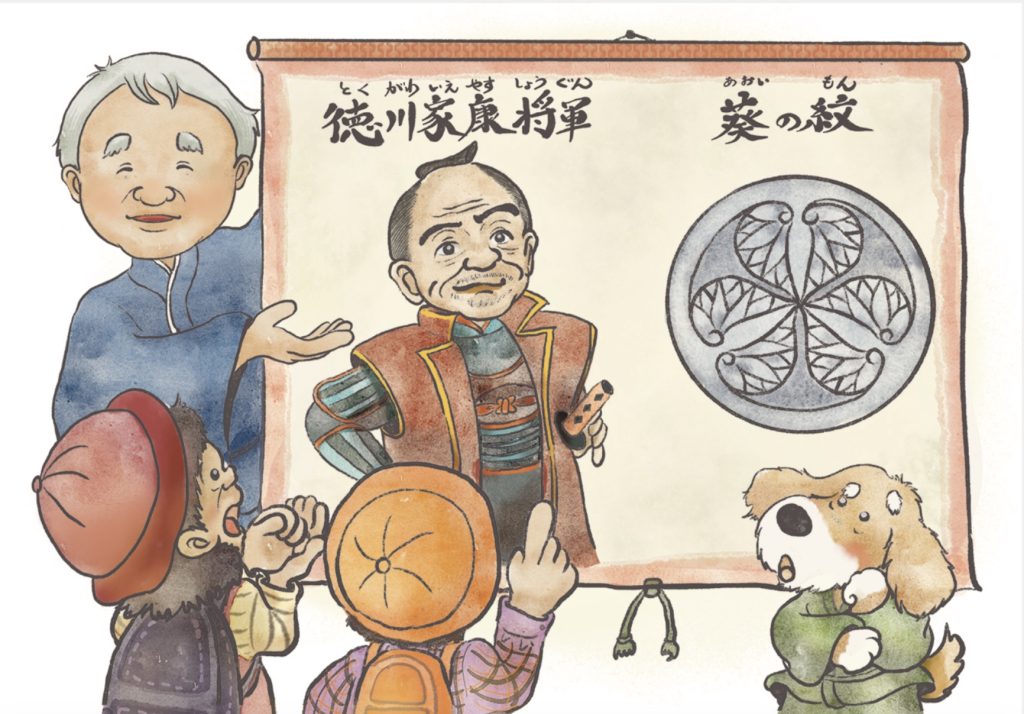お寺の鐘
もともとお寺の鐘は、法要の集会の合図として撞かれるとともに、時を知らせるためでもありました。時計が無かった時代に、時刻を知る一つの手段でもあったのです。特に夜明けと日没を知らせてくれるものとして、撞く時刻は夜明けと夕暮れ頃だったようです。畑仕事をしている人々が多かった時代には、欠かせない知らせだったのでしょう。現在の時刻ではおよそ朝夕六時頃となります。
真宗本廟(東本願寺)では朝のお勤め(晨朝)の合図として十一回撞かれています。また、報恩講ではお勤めの始まる一時間前にも撞かれます。参詣の皆さんにもうすぐお勤めが始まりますよとの声かけだった訳です。
大きさは様々ですが、「梵鐘」と呼ばれる大きなものは、境内にある鐘楼堂や鐘楼門に吊下げ、撞木という木製の太い棒で撞き鳴らします。
私たちの願立寺には梵鐘はありませんが境内の角に太鼓楼があって、大きな太鼓がその代わりをしております。秋の報恩講や春の永代経法要のお勤めの一時間前に、五つ・打上打ち下げ・三つのリズムで太鼓を打ちます。皆さんが着席された頃、勤行五分前に「喚鐘」を同じく五三のリズムで撞きます。喚鐘は梵鐘と比べると小ぶりな鐘ですが法要行事の始まり等を知らせる大切な鐘です。
梵鐘のないお寺もあります。それは第二次世界大戦時に出された「金属類回収令」の影響がありました。当時、軍需生産原料として必要な金属を集めるため、お寺の鐘や仏具をはじめ、家庭の鍋や釜にいたるまで供出されたと聞きます。また、昨今住宅密集地では大晦日の梵鐘の音も騒音とされ、苦情により昼に撞かれている所もあるようです。現代社会の生活事情が表れているようです。なんともはや。
※出典参考「仏教・仏事のはてな?」東本願寺