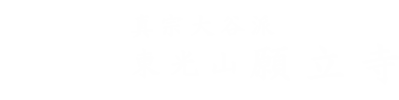料理家の土井善晴さんが、最近提案されておられます。
世の中があまりにも贅沢になりすぎて、おかず5〜6品が
作り手に大きなプレッシャーにもなっているそうです。
食事の原点は質素な「一汁一菜」でよい。
ご飯と具の入った味噌汁、お漬け物。
それで十分!という提案。
蓮如さんは「お斎」(おとき)を大切にされたそうです。
お斎は、法事の後、皆さんでいただく食事のことです。
勤行、法話、そしてお斎があって法事が成立するのです。
法事は難しいお経で始まるものの、法話で意味や内容にふれ
そして、食事をしながらさらに噛み砕いていく。
膝をつき合わせて話し合いながら、信心を確かめ合うことを
大事にされたのでしょう。
その時の食事が、まさに「一汁一菜」
お参りのご門徒に尋ねました。
今までで、「一番おいしかったのは何ですか?」と
皆さん、うーうーん・・となんとか思い出し
搾り出した記憶には
・疎開先で父がつくってくれた「蒸しパン」
・戦争中、弟と食べた「おにぎり」
・戦後、進駐軍から貰った「お菓子」
・小さい頃、近鉄百貨店で食べた「オムライス」
それぞれの話には心に沁みる思い出がありました。
恥ずかしながら、住職は
・子供の頃はじめて食べた「チキンラーメン」
でした。
姉と3分待って蓋を開けた一口は衝撃だったのです。
どれも、今、飽食の時代にはお世辞にも
美味しいご馳走とは言えないかもしれません。
でも、その時は最高に美味しかったのです。
一番美味しかったのは
決して豪華な御膳ではなかったのです。